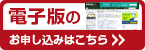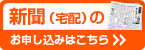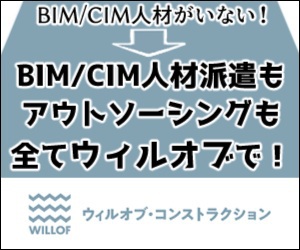「私たちの主張」は、建設産業がもたらす夢やあこがれ、建設業を選んだ動機など、建設産業のイメージアップにつながるメッセージを作文形式で募る取り組み。1月27日に国土交通大臣賞2点、土地・建設産業局長賞3点が表彰された。「私たちの主張」の受賞作を紹介する。
建設業の3K (株)新庄砕石工業所 柿崎赳 −国土交通大臣賞−
「建設業って3Kなんでしょう?」
それは大学時代の友人達と久々に集まり、居酒屋で飲んでいる時のことだった。私は友人達に、建設業で働いていると言うと、返す刀でこう言われた。私は心の中で「やはりまた言われたか・・・。」と呟いた。
こう誰しもに言われると、もはや建設業の合い言葉ではないかと思えてくる。建設業は、「きつい」・「汚い」・「危険」。これら3つを合わせて通称「3K」。残念ながらこれが世間の目というやつだ。私はそれを言われるとムカっとするが、言い返す言葉が上手く出てこない。それは内心、私自身も建設業のイメージが3Kに近いものと感じていたからだ。
その日も私は、自分でも何か良く分からない事を言い、有耶無耶にして話題を逸らした。私はその場ではっきりと、「建設業は本当は素晴らしい職業なんだ!」と言う事が出来なかった。私は何かモヤモヤしたまま、友達と別れた。
そんなモヤモヤを抱えていても日々の仕事はやってくる。それは護岸の復旧工事をしている時の事だった。今まで体験した事のない凄まじい揺れが現場を襲った。私は堤防の上で立っている事も出来なかった。それは後に「東日本大震災」と名付けられる大地震だ。幸い、私の住む山形県の被害はそれほどではなかった。しかし、すぐ隣の宮城県は壊滅的な被害を被っていた。
地震から2週間ほど経ち、山形県では大分落ち着きが見え始めた。我が社では被害復旧のため、石巻市に重機を搬入しようかとの話が出ていた。先だって私は被災地の石巻市に行く事になった。私はテレビで石巻市の被害を見ていたので、「何とか石巻の人の力になりたい。よーし、やってやろう!と熱い気持ちになっていた。だが実際に石巻市に着いてみると、そこは想像を遙かに超える光景だった。もはやここに何があったのか分からない。果てしない瓦礫の山。私は茫然と立ち尽くした。これはもうどうしようもないのではないか・・・。正直そう思ったのだ。
来る前の熱い気持ちも、いつの間にか何処かに消えてしまったようだ。私はしばらく街中を、と言うか瓦礫の中をボーッと歩いていた。しかしそんな私を、ハッとさせる光景が目に入ってきた。それは陸上自衛隊と建設業者が、災害復旧のため必死に瓦礫処理をしている姿だ。自衛隊が派遣されたのは知っていたが、まさか建設業者がこんなに早く来ているとは思わなかった。その建設業者の必死な姿に、私は心の底から「感動」した。同時に、言葉では言い表せない熱いものがジワジワ体を駆け巡った。その時、すぐ側にいた地元の人がこう言ってきた。
「自衛隊と建設業者には、本当に感謝しているよ。自分たちも危ないのにこんなに頑張ってくれて・・・。」
私は建設業に携わり、こんなに心のこもった「感謝」の言葉を聞いたのは初めてだ。いや、ここまで心のこもった感謝は生まれてこのかた聞いた事が無い。無論、それは作業をしている人たちへの感謝の言葉なのだが、同業者だからか、何故か私も誇らしくなってしまった。その時私は思った。困っている人にこんなに貢献出来る建設業が本当に誇らしく、なんて凄い職業なのかと。以前からあった私の中のモヤモヤが消えた瞬間である。この時から、私の中の3Kは全く違う形のものとなった。
「感動」、「感謝」、「貢献」。私が自然と建設業に感じた言葉だ。それは私の中でも悪いイメージだった建設業をガラリと変えてくれた新しい「3K」となった。
今では建設業と言えば、悪いイメージが先行されがちだ。しかし、建設業の役割は計り知れないものがある。橋や道路等の公共事業だけではない。災害が起こった時のライフラインの確保や復旧活動等、常に地域には欠かせない存在なのだ。被災者にとって、それがどれだけ心強い存在か。今回私は身を持って感じる事が出来た。
地震から半年以上過ぎたが、それでも被災地の復旧作業はまだまだだ。困っている人も山程いる。建設業がやらねば誰がやるのだ。衰退産業だと言っている場合ではない。東北も建設業も、これからもっともっと盛り上げて行かなければならない。その一員になるために、私も日々努力し勉強して行こうと思う。もちろん不安な事もあるし、大変な事も沢山あるだろう。でも大丈夫。私に以前の様なモヤモヤは無い。私には心強い、新しい「3K」がついている。
建設業のイメージを変えるためには、建設業者が自ら立ち上がるしかない。私はまず、この新しい「3K」を私の周りから少しずつ広めて行きたいと思う。最後になるがこれだけははっきりと言いたい。
「建設業は本当に素晴らしい職業です!」
建物を造る喜び 会津土建(株) 小山理絵 −国土交通大臣賞−
建物の魅力は同じ物が一つもないという事だと思います。同じ用途の建物でも設計者によってさまざまな形になり、施工者は何通りもある施工方法から、現場にあった方法を選びます。私は女性ですが、建設現場の仕事に興味を持ち地元の建設会社に入社しました。
私は、高校の授業を通して建物を造ることに興味を持つようになりました。授業には建築施工の実習もあり、コンクリートを作り、圧縮強度の試験をしたり、自分たちで加工した木材で小さな小屋を建てたりしました。実習などで物を一から作る楽しさを感じ、いつしか職業にしたいと強く思うようになりました。
私が生まれ育った町にはお城があり、城下町の雰囲気が色濃く残っています。入社して初めての現場は、お城から目と鼻の先にあり、その景観にとてもマッチした木造二階建てのカフェレストランでした。私はその現場に着工から引き渡しまで携わりました。高校の授業で木造の勉強もしていたので、勉強したことを活かして頑張ろうと思っていました。
しかし、勉強していたことと実際の建設現場は、私が思っていた以上に違いがあり、驚きました。まず、躯体の工法が普通の木造住宅とは異なり、接合金物による工法でした。仕口や継手が無く欠損部が少ないため、木材の持つ本来の強度を十分に活かすことの出来る工法でした。そして日本で初めて、クロスラミナパネルという繊維直行型の積層パネルをオーストリアから輸入し、使用しました。木造九階建てを実現した構造材で、断熱性や気密性にも優れているので、厳しい冬でも暖房にかかるエネルギーを抑えることができます。
ヨーロッパでは木材製品を使用し、地球温暖化防止対策に積極的に取り組んでいると言われています。この建物の設計コンセプトが「森林保全を目的とした環境への負荷軽減を目指した木造建築」であることから、このパネルの採用が決められました。初めての現場で、私はまだまだ学ばなければならないことが山ほどあると感じました。知らなかったことを学んでいくことで、ますます建築の魅力に引き込まれていくのを、日々実感しています。
最初の頃は、学校と社会の違いに戸惑いを感じながら、私の父くらいの年齢の職人さんとコミュニケーションをとるのはとても難しく、たくさんの失敗をしました。職人さんとは話しづらい印象がありましたが、私が思っていた以上に現場の職人さんたちは優しい方ばかりで、どんな失敗をした後でも、「次は同じ失敗をするなよ。」と励ましてくれました。未熟で、右も左もわからなかった当時の私にとって、その励ましはとても大きな力になりました。
最初の現場が竣工した時は、建主が毎日カフェの椅子に座り、来る人来る人に自慢げに建物の説明をしていました。私はその姿を見て、胸の熱くなる思いがしました。施工管理は「きつい」、「汚い」、「危険」の3K職場と言われる仕事ですが、やりがいがあり、完成した時の喜びは何物にも代えられません。設計者も施工者も、建物が完成した時は建主以上に喜びを感じるものだと思います。
一つの建物に沢山の人が関わりますが、着工前から引き渡しまで全工程に携わる施工管理者は、建物を建てる上で、建主と設計者と職人をつなぐ大事な役割だと思います。私が感じていたものづくりの楽しさは、自分が満足するだけのものでしたが、実際にはお客様がいて、職人さんとやり取りをしながら建てた建物は、自分だけでなく、多くの人に喜びを与えられるものだと感じました。
私は女性で、男性に比べて力もなく、結婚して子供が出来れば家事や育児をしなければなりません。大きなハンディキャップがありますが、それを乗り越え、建設現場は男性だけでなく、女性も活躍できる職場だということを多くの人にアピールして、建物を造る喜びを多くの人と共感したいです。
建物は二度と同じ物を作ることが出来ませんが、私が年老いても、「ここは私が建てた建物だ。」と胸を張って言える作品を、一つでも多く残していきたいと思います。
仕事に対する思い 銅谷建設(株) 大泉尚之 −土地・建設産業局長賞−
私が建設業に携わって一年が経ちました。たったの一年ですが、今年の一年間は今まで先輩方が経験してきた一年とは違ったと思います。
3月11日、東日本大震災により私たちの生活する宮城県は大きな被害を受けました。請け負っていた現場はもちろん、多くの一般住宅も簡単には直せないほどの被害を受けていました。宮城は直すだけでなく、沿岸部で津波の被害を受けた住宅では解体作業も多く残されていました。
私自身も沢山の被災現場を見てきました。まだ一年しか業務をしていなく、経験はもちろん、知識も技術もないに等しい。けれど、先輩達だけでは手に負えない量の現場の数だったので、数件の現場を担当することになりました。
私が担当したのは一般住宅でした。多くの家はお年寄りの方々が多く、最初の頃は震災直後でもあったし、他人を家の中に入れるという不安もあったのか、作業を始める時と終わる時の挨拶程度しか会話はありませんでした。でも、次第に色々話してくれるようになったり、一服の時間にお菓子やお茶を出してくれたりして、少しずつ心を開いてくれている感じがしました。正直、建設業に入ってこれまで人との繋がりがあるとは思っていませんでした。建設業に入る前と後、そして震災後、たった二年でこんなにも建設に対しての考え方が変わってくるとは思っていませんでした。そして、自分自身が建設に携わっている意味についても。
私の地元も沿岸地域だったため、壊滅的な被害を受けました。もちろん、解体の依頼は私の会社にもきました。テレビや新聞など、メディアを通してでも津波の映像や写真を見るのは辛かったのに、まさか解体までやることになるとは思ってもいませんでした。実際に解体に携わることはありませんでしたが、会社での打ち合わせの度に地元の解体の話を聞いたり、解体場所の地図を見たら友人や知人の家だったり、休日に友人と地元に足を運べば自分の会社の旗や社名を目にしたり、正直辛かったです。足を運ぶ度に瓦礫は片付けられ、わずかに残った民家でさえ壊され、無くなっていく姿、ただでさえ思い出の物は全て流されて無くなったのに、わずかに残っていた町並みすら日に日に無くなっていく。震災後から、思い出を無くし、家族を亡くし、悲しみに暮れる人を何人も見てきた。自分の住んでいた家も、部屋も、大好きだった景色・風景ですら、徐々に薄れていく恐怖も、そんな自分に対する嫌悪感も知っている。そんな多くの人々の思い出を壊すことに、直接は関わっていなくても自分が加担しているような気がして、みんなを裏切っているような気がして辛かった。
でも、「全然知らない人にやってもらうより、お前の会社でやってもらった方が、少なくともお前は俺たちの気持ちを分かってくれている。誰も何も思わず壊されるより良い。」 そう言ってもらえたことが嬉しかったし、私が建設業に憧れを抱いたときを思い出しました。
誰かに感謝されるような仕事をしたい。少しでも誰かを笑顔に、幸せな気持ちにしたいと思っていました。今回の震災で、多くの人の笑顔が見られた。多くの人に感謝された。辛いことも大変な事も多いけど、喜ばれたとき感謝されたときは本当に嬉しく思える仕事。これからも、誰かに喜んでもらえるような仕事をしていきたいです。
建築という道へ進んで (株)早野組 杉田瑞穂 −土地・建設産業局長賞−
子供の頃の将来の夢は男の子のように大工になることでした。家が工務店で庭に仕事場があったので、小さい頃からそこが遊び場でした。住んでいる家は祖父が建てた家で、普段使っているテーブルや椅子、ベッドなども父が造ったものを使っていました。仕事をしている父の姿を見て育ち、なんでも造りだせる大工という仕事に憧れ、私も自然と大工になりたいと考えるようになりました。
高校を卒業して建築の専門学校に進み、設計中心の勉強をしていましたがいざ就職を考えた時、やはり大工になり、実際に自分で家を造りたいと考えるようになりました。両親には最初反対されましたが、どうしても挑戦してみたいという自分の気持ちを伝え、職業訓練校で大工の基礎を一年間学ばせてもらいました。訓練校では「のみ」や「かんな」の研ぎ方、道具の使い方、仕口・継手の練習など基礎を一から学び、最終的にクラス全員で建物を一棟建てるまでの実習を行い、建物が完成する喜びを味わうことができました。
職業訓練校を卒業後は、東京の工務店に就職し大工として働き始めました。初めて入った現場は住宅の改築工事で、親方は七十歳近くのいかにも頑固な職人という方でした。最初は、「こんな女の子に何ができるのか。」という感じで全く相手にされず、また、自分も何をしたらいいのか分からずにいました。とりあえず、「できることから始めよう。」と毎日ホウキを片手に目についたゴミを掃除しながら職人さんの仕事を見ている日々でしたが、挨拶だけは常に忘れずに元気よく行っていました。一週間経つと話しかけてもらえるようになり、少しずつですが仕事の手伝いをやらせてもらえるようになりました。大半は掃除で終わりましたが、初めて働いた現場として今でも鮮明に記憶に残っています。大工見習いとして働きだしましたが、最初のうちはボード一枚を運ぶのがやっとで、天井を一人で貼るのに苦労し、人の何倍も時間がかかりました。たかい所も得意では無かったので足場上での作業は常に注意し、新築の建方時には屋根を敷くまでは緊張の連続でした。
周囲からも何故この仕事をやっているのかとよく聞かれましたが、「この仕事が好きだから。」といつも笑って答えていました。それまで何も無い空間が日ごとに人の住む空間へと変わっていく様子は楽しく、また、そこにわずかでも自分の力が加わっている事は目に見える達成感がありました。完成した建物を見て喜んでくれる施主の笑顔に応えられるよう、自分も腕を磨いていきたいと強く考えるようになりました。大工として働いたのは四年間でしたが、とても充実した期間を過ごすことができました。
住宅以外の建築にも携わりたいと考え、現在は地元の建設会社に就職し、積算の仕事に就いています。毎日机に向かい図面とパソコンに向き合う作業に最初は戸惑いも感じましたが、やっていくうちに建物を建てる上で必要不可欠な仕事だと分かりました。
完成するのにどの位の費用が必要か図面上で読み取らなければなりません。間違った積算をしてしまうとそのまま現場に影響が出てしまう重要な仕事です。必要な材料、数量の拾いを行うだけではなく、設計事務所への質問点の確認を行うことや、決められた期間内にやらなければならない仕事量は想像以上でした。現場で働いていた時にはその現場で必要な材料がそこにあるのは当たり前のように感じて仕事をしていましたが、積算の仕事があって初めて現場が動き出すのだと今更ながら気付き、より慎重に積算を行うことを日々心がけています。
また、実際の現場を経験して更に業務に活かせるようにと、現場監督の補助の仕事をさせてもらう機会がありました。大工をしていた時、監督はただ現場にいるだけで何もしていないように感じていましたが、施工期間が決まっている中で材料や人の手配、施工図面の確認や、職人や施主、設計事務所との打ち合わせ、また、周辺環境への配慮や地域住民との交流を行う等、現場がスムーズに運営されるために裏で行っている作業は幅広く、また専門的な知識も必要な仕事であると実感しました。
様々な経験をする中で、建物一棟が完成するのには職人さんだけでなく、設計の人達や営業の人、積算業務を行う人など多くの人の力が加わっているのだと気付けました。
このような多くの人が関わって一つの建物を造り上げていく建築という仕事は、どの立場で関わっていても、建物が完成していく上で何一つ欠ける事の出来ない重みのあるものです。また、関わった想いが強いほど完成した時の喜びは大きく、達成感があります。
そんな建築の世界に是非、より多くの人たちに足を踏み入れてもらい、多くの喜びを感じてもらいたいと思います。
少年と老人から学んだ思い 永井建設(株) 村瀬淳 −土地・建設産業局長賞−
幼い頃、宇宙飛行士に憧れ、飛行機のパイロットに憧れ、消防士に憧れた。そして、小学生の頃からものづくりに興味を持ち、スケールの大きさに憧れて建設業を目指した。
当時は好景気の中、建設機械を手足のように操作して何もなかった所に道路や建築物を完成させていくおじさん達を見ていた。
ふと、気付くと、今の自分はそのおじさん達と同じ年頃、同じ立場にいました。
そんなことを気付いたのは、数年前のことです。その頃はある道路改良工事に従事しており、忙しい日々の中、夕方になると決まって愛犬と散歩に来る少年と親しく話すようになりました。
ある日、その少年が現場事務所を訪ねて、悲しい顔で私に訴えてきました。愛犬が交通事故で死んでしまったと言うのです。慰めの言葉を掛けてみましたが、彼の悲しみを取り除くことはできませんでした。
その頃から少年は現場に顔を出さなくなりましたが、工事はどんどん進捗して完成間際まで辿りつきました。
最後の舗装作業の日、トラブルで夜までの作業を実施する必要があったため、地元住民に残業する旨の了解を得ようと各宅を挨拶して回っていました。
その中にあの少年の家もあって、少し気になっていたので家の方に少年の様子を聞いてみると、あれから少年は一生懸命勉強するようになり、「工事のおじさんになりたい」と言っていると聞きました。 何がどうなって少年はそんな考えになったのか見当もつきませんでしたが、涙が出てくるくらい嬉しく思えました。
結局その日は夜の9時まで作業を行い、片付けをしている時に、老人が作業員全員分のラーメンを持って現れました。私達は食事を取ることも忘れていたので大変嬉しく思うのと同時に非常に助かりました。
ラーメンを頂きながら聞くと、老人はあの少年の祖父でした。老人の話によると、今、私達が施工している道路改良工事は、地元が30年以上前から望んでいる道路であり、近くの歩道の無い幹線道路では事故が多く、少年の愛犬もそこで亡くなったということでした。更に、少年は私達が一生懸命に、そして楽しそうに作業を行い、あっという間に景色を変えさせてしまうパワーを持つ建設業に憧れを抱いているという事でした。
私達作業員一同は、感動と共に、もっと早く工事を終わらせれば少年の愛犬を救うことができたのではないか?と自分を責めました。
後日、工事は完成し、道路は供用を開始しました。私は老人と少年の家に出向き、お世話になった御礼を伝えました。そのとき、老人は「私には夢があって、新しい道路に車が増えたら、ここでコンビニでもやろうと思っているんだ。」と言いました。私の父親と同じくらいの老人が、道路と共に新しい夢を抱いている。自分たちの仕事はただ社会資本を作るだけじゃなく、人々に夢を持たせることのできる職業なんだと思いました。
昨日、この文章を書くにあたり、当時の現場に久しぶりに出向いてみると見事コンビニは営業しており、深夜のバイトの方によれば、あの老人は昨年他界されたと聞きました。少年については工業高校で土木の勉強をしているとわかりました。
私達が携わった道路が、地域やその道路を利用する人にとって便利であるだけじゃなく、夢を与えること、夢を実現させることができることに今一度気付かされました。
この工事で私は多くのことを学びました。もちろん業務上の知識や体験もありますが、地域の方々の夢や将来に対する思いが社会資本の建設を後押ししていること、自分たち建設業の技術屋は、その社会資本が長く愛されていけるように、しっかりとした仕事をすることが大切なんだと強く感じました。