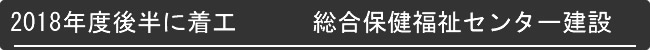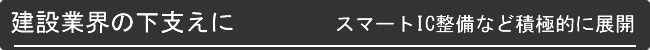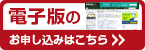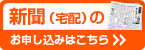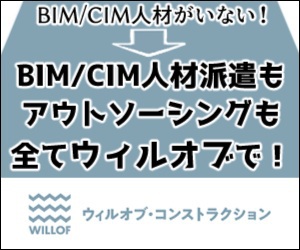「市民の声を大切に・健康日本一・災害に強い安全安心・持続可能な子育て支援と福祉の充実」を市政運営の柱に『温か笑顔の東温市』実現に向け、各種施策に取り組む加藤章市長に意気込みを聞いた。
―道路網の整備や上下水道について見通しをお聞かせください。
事業継続中の愛媛医療センター前の横河原10号線について、拡幅整備と通学路の安全確保のため早期の完成を目指して事業を進めます。ライフラインとして特に重要な上水道につきましては、近い将来発生が予測される南海トラフ巨大地震などへの備えとして、災害に強い施設の構築が急務であるといわれています。市民の皆さまに安全な水を安定的に供給するため、1999年度に着手した統合簡易水道事業が2017年度に完了し、今後は適切な資産管理を行いつつ施設の長寿命化を図るとともに、次期事業計画の策定に向けた基礎調査を進めます。
公共下水道については17年度末の全体計画に対する面積整備率が重信処理区で約64%、川内処理区では約76%となり、市全体で約67%の進捗ですが、引き続き投資効果の高い住宅密集地から整備を進めます。また、公営企業の一つである公共下水道事業も上水道事業同様に地方公営企業法の適用を行うよう要請があり、20年度からの企業会計化を目指して移行事務に取り組んでいます。
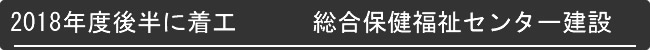
―安全・安心な町づくりを目指しているとのことですが、公共施設の整備については。
本格的に少子高齢・人口減少社会が進行する中、誰もが健康で安心して暮せる社会づくりが必要です。そのため、東温市の保健・福祉・子育て業務の拠点となる「(仮称)東温市総合保健福祉センター」を建設します。造成に8月から着手し、本体工は本年度後半から着手する予定です。19年度中の竣工を目指します。
学校施設の耐震化率は既に100%を達成しておりますので、引き続き年次計画に基づき大規模改修などを行います。本年度は老朽化が著しい川上小学校プールについて既存のプールの東側に新たなプールを造り、完成後に既存のプールを取り壊します。新設するプールはFRP製25メートル(8レーン)と幼児・低学年用プールを予定しています。概算事業費は2億8000万円程度を見込んでおり、建物は鉄筋コンクリート一部鉄骨造延べ1723平方メートルを想定、また付属する施設として更衣室やトイレ、新たに観覧席192席を整備し新たなプールでは市内小学校の水泳記録会を行うこととしています。
保育所、幼稚園についても既に耐震化率が100%を達成しています。18年度において保育所改修計画の見直しや学校など施設個別計画の策定により、改修内容や改修時期などについて検討し定期的に改善していく予定です。本年度は双葉保育所の大規模改修を実施し、保育室の充実を図るために照明器具のLED化やロッカーなど建具の集約、畳スペースのバリアフリー化などを行い、低年齢児も安心して遊べるスペースを確保します。また、厨房(ちゅうぼう)の改修では床下地材を補強するとともに、一部設備の更新や施設内部での区割り変更によるスペースの拡張により調理作業の効率化を図ります。川上幼稚園においても照明器具のLED化やロッカーなど建具の集約および外部テラスの改修などを行い幼児教育の充実を図ります。
川内体育センターは、生涯スポーツの拠点施設の一つとして年間3万人以上の市民などにご利用いただいていますが、施設各所に劣化が見られるため、大規模改修を本年度行います。主な改修内容としては照明のLED化、屋根防水、外壁塗装、床改修、駐車場舗装などを予定しています。
―スマートインターチェンジ(IC)および工業団地の整備に向けた構想については。
スマートIC整備により本市や松山都市圏のみならず広域的な整備効果が期待されます。(1)本市から松山市東部にかけて約200の物流事業者が集積していることから「松山都市圏の物流活動の活性化」(2)市内企業の高速アクセス性の向上や企業誘致による「地域経済活動の発展」(3)交通渋滞が著しい松山ICへのアクセスルート(国道33号)の交通量分散による「松山都市圏の渋滞緩和」(4)市内に複数立地している中核医療施設への「アクセス性向上による医療活動の支援」(5)陸上自衛隊松山駐屯地や愛媛県警察機動隊の迅速な被災地への到着に寄与する「災害発生時の救急活動の支援」。このスマートICにつきましては、ラウンドアバウト型の料金所の導入を計画しており、2018年度の新規事業化に向け2018年7月に地区協議会を開催し国・NEXCOなどへ実施計画書を提出するとともに国へ連結許可申請書を提出したところです。また、さらなる企業誘致を進めていくためスマートICの整備と並行して、企業立地の受け皿となる新たな工業団地の整備について21年度の分譲開始を目標に17年度から東温市土地開発公社において事業に着手し、本年度は各種手続き並びに用地取得のため関係権利者との協議を進めています。
―大規模災害などに対する取り組みについては。
今後30年以内には70〜80%の確立で南海トラフ巨大地震が発生するといわれています。また、異常気象に伴う気象災害も全国各地で相次いで発生しており、このたびの「平成30年7月豪雨」災害では県内でも南予地域を中心に甚大な被害が発生し、復旧に向けて住民・行政が一体となって取り組んでいるところです。本市におきましては幸いにも人的被害また大規模な家屋被害の発生はなく大事には至りませんでしたが、いつ発生するか分からない災害に対して強い安全安心のまちづくりを進めるに当たり「災害は必ずやってくる」との認識を持ち、日頃から備えを十分にすることが必要不可欠です。市といたしましても、突然に襲い来る災害に対し日頃からできる限りの備えを行っていますが、いざという時には地域の「自助」「共助」の力が大変重要となります。「災害に強い安全安心のまちづくり」を目指し、地域の皆さまに初期消火活動、被災者の救出・救助、情報の収集や避難所の運営などの重要な役割を担っていただくため、市内35の行政区全てに自主防災組織を完備し各組織で地域防災活動を推進しているところですが、今後は自主防災組織相互の連携を強化するとともに、行政、地域、関係機関が一体となった防災体制の整備を一層推進してまいりたいと考えています。
また、東温市99カ所のため池のうち23カ所を防災重点ため池と位置付け、「ため池ハザードマップ」を作成することとし、12年度に11カ所のハザードマップを作成しています。本年度は残り12カ所を作成します。このたびの「平成30年7月豪雨」では6府県23カ所のため池が決壊し各地に甚大な被害をもたらし、現在、復旧作業が進められています。自然災害は「いつ・どこで」起きるか分かりません。特にため池による被害は命に関わりますので防災を意識した地域づくりなどに「ため池ハザードマップ」を活用いただきたいと考えています。
―社会基盤インフラ(橋梁、トンネル)の長寿命化への取り組みについては。
市内の橋梁などの既存インフラについては長寿命化を図るため、従来の事後的な管理から計画的かつ効率的な予防管理へ転換し、修繕などにかかる経費のコスト縮減を図るとともに施設の安全性・信頼性の確保を進めます。また、長寿命化修繕計画を策定することにより、従来の事後的修繕から計画的かつ効率的な予防修繕へ転換し、修繕などにかかる経費のコスト縮減を図ってまいります。橋梁については本年度で点検が終了することから19年度に長寿命化修繕計画を策定し20年度より順次、修繕委託設計および工事を実施する予定です。また2カ所のトンネルについては既に長寿命化修繕計画を策定しており19年度に修繕委託設計を行い20年度より修繕工事を実施する予定です。
―技術者確保・育成については。
東北復興や東京五輪などにより、ゼネコンをはじめとする民間建設業界に勢いがあることなどから、自治体における土木などの技術職の採用試験において採用応募者が採用予定数に満たない事例も出始めていると聞き及んでいます。本市におきましては、県都に隣接しているという地理的な側面などから今のところそのような状況には至っていませんが、今後におきましては必要に応じて採用試験方法の見直しなども含めて検討し、よりよい人材の確保に努めたいと考えています。
また、行政の技術職員は地域のインフラ整備・維持の担い手であると同時に地域社会の安全・安心の確保が使命とされており、昨今の急激な社会の変革や高度・専門化する建設行政を柔軟かつ効果的に推進する必要があります。このため本年度からNPO法人愛媛県建設技術支援センターの協力を得て近隣市町との共同開催により3カ年に約30項目の「技術研修」を実施することとしており多様化する行政課題や住民ニーズを的確に捉えるとともに、より一層のコスト意識と公共工事の適正な施工につながるものと思っています。
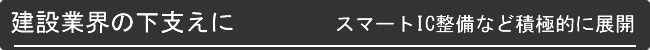
―建設業界へメッセージを。
2011年に起こった大震災の復興事業や東京五輪の決定により、建設業界の需要は高まり続けています。業界にとっては大変好ましい傾向と思われますが、それに伴い人手不足に陥っています。特に技術者や技能者の不足が深刻で、震災の復興事業は予定よりも進捗が遅れているとされています。また、建設業界に就職する若者は減少の一途をたどっているとされ、東京五輪が開催される20年までに合計で15万人もの労働力が不足すると予想されており、長期的な目で見ると業界は厳しい経営環境に置かれていると考えています。しかしながら地方の建設業界においては基幹産業として良質なインフラ整備や地域経済の活性化、雇用の確保はもとより、災害時における救援・復旧活動など市民の安全・安心のためにも必要不可欠な産業であり、建設業界が担う役割は大変重要であります。このため市では歳入の増加が見込めない厳しい状況下においても必要不可欠であるインフラ整備としてスマートICの整備をはじめ、総合保健福祉センターの建設、学校施設などの環境整備、道路・橋梁施設の長寿命化、上下水道事業などの公共事業を積極的に展開することにより、建設業界の下支えになればと思っています」
このページのトップへ
(2018/8/31)