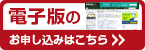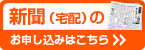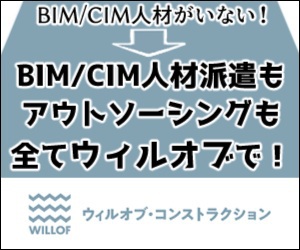Catch-up <2022年12月〜2023年1月号>
建設業に関わるトピックスを分かりやすく解説するコラム『Catch-up』バックナンバーです。
若者が将来を描ける業界に CCUSレベル別に賃金目安 2022/12/2
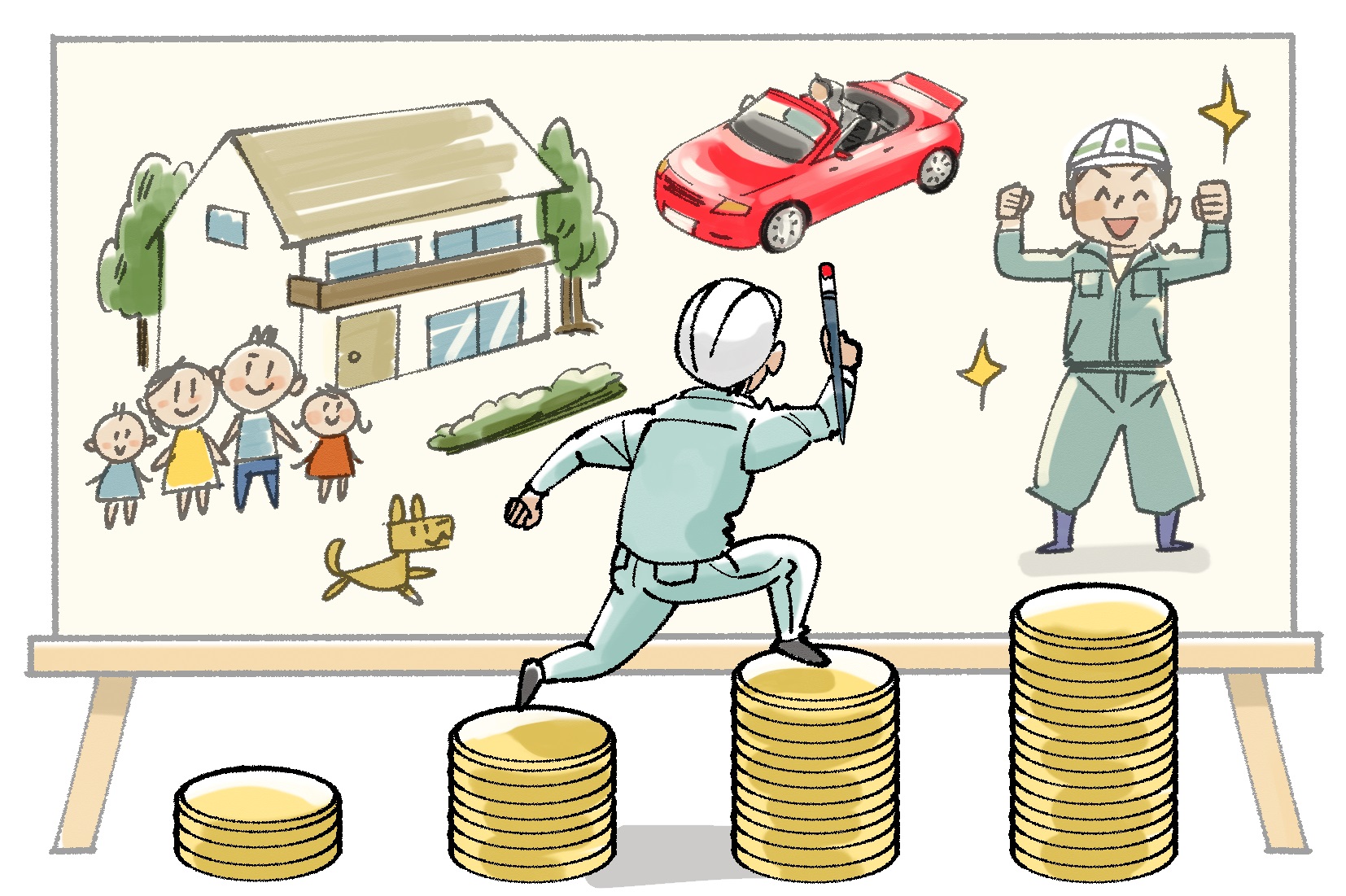
建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録技能者数が100万人を超え、技能者の3人に1人が利用する水準に至った。2019年の運用開始から3年半余りでの大台突破だ。斉藤鉄夫国土交通相は、「技能者のレベル別の賃金目安を示すことで、各職種の賃金の上昇を促していく」と今後を展望した。国交相が定例会見でCCUSに関して報告するのは異例だ。
CCUSは、技能者の資格や就業履歴などから、技能レベルを4段階で評価し、適切な処遇につなげていくシステム。建設業振興基金が運用している。登録技能者数は10月末現在で102万4269人。全国の建設技能者の3分の1が登録したことになるという。
技能者の登録が一定程度進んだことを受け、国交省はCCUSの技能レベル別、職種別の賃金目安をまとめる。担当者によると「公共事業設計労務単価の結果も参考にして、来夏までに具体的な賃金目安を示す」とする。
経験やスキルを高めた技能者が得ることができる具体的な賃金水準を示すことで、若い技能者が自らのキャリア形成を見通し、建設業界で働き続けた場合の将来像を描けるようにする。建設技能者の年齢層を見ると、60歳以上が約80万人で全体の25%超を占める。一方で30歳未満は約37万人と全体の12%にとどまる。若年技能者の離職を防ぐ必要がある。
国内の15歳から64歳までの生産年齢人口は今後10年で550万人、20年では1500万人も減るとされる。企業間、産業間の人材獲得競争は間違いなく激烈になる。芝浦工業大学教授の蟹澤宏剛氏は、「建設業に当てはめると自然減だけで、10年で37万人、20年で100万人減少する」と予測し、低賃金で長時間労働、休暇が少ないといった建設技能者の処遇を問題視する。
ただ、担い手の確保では明るい兆しも見えてきた。厚生労働省の調査によると、ここ数年、建設業では入職者数が離職者数を上回る状況が続いている。20〜30歳代の転職入職者も増えているという。建設業は、国民の安全・安心な暮らしを支える重要な役割を持つ。技術の継承とともに産業を持続していくためにもこの流れを確実なものにしていかなければならない。
斉藤国交相は、「職人が誇りを持って働ける現場を作っていくために何としてもCCUSを成功させたい」と会見を結んだ。
経営者保証の融資慣行 事業承継の“重荷”に 2022/12/16

「後継者の候補はいるのに、事業の承継を拒否されている」。こんな悩みを抱える経営者は少なくない。その理由として、経営者個人が企業の連帯保証人となる「経営者保証」の影響が指摘されている。全国の建設業経営者の平均年齢は60歳に迫っており、事業承継が円滑に進まなければ、担い手不足に拍車をかけかねない。経営者保証によらない融資慣行の確立は喫緊の課題だ。
経営者保証は企業の資金調達を円滑にし、また慎重な経営を促す面もある。しかし、中小企業基盤整備機構が行ったアンケートでは、中小企業で後継者候補がいるにも関わらず承継を拒否されている理由の65%は経営者保証にあるという。企業が倒産したとき、経営者が多額の弁済を迫られることへの不安は根強い。
設備や人材などの投資に踏み切ろうとしても、融資に経営者保証を求められるため制約されがちになるという分析もある。前向きな投資をためらうようになれば、残業時間の罰則付き上限規制の適用が迫る建設業において不可欠な生産性の向上もおぼつかない。
こうした課題もあって、全国銀行協会と日本商工会議所は経営者保証によらない融資を促進するためのガイドラインを2013年に策定。政府も事業承継時の経営者保証解除を後押しする信用保証制度の整備を進めてきた。
しかし、今も金融機関が中小企業への融資で経営者保証を求める慣行は広く浸透している。日本政策金融公庫が9月に行った調査でも、メインバンクからの借入で経営者保証を提供している割合は75%にもなる。経営者保証に関するガイドラインに基づき、メインバンクから経営者保証の必要性や解除の可能性に関する説明を受けたという企業は47%と半数以下にとどまる。説明を受けたという企業も、「口頭説明のみ」だった割合が39%を占めており、十分に理解が及んだかは不透明だ。
こうした状況を打開するため、金融庁は金融機関の「総合的な監督指針」を改正する。保証契約を結ぶ際、保証が必要となる理由や、解除につながる改善策の説明などを金融機関に求める。23年4月から適用を予定している。
より抜本的な対策も検討中だ。不動産・設備の担保や個人保証によらない融資制度の検討会を設置。企業の事業全体を対象とした「事業成長担保権」(仮称)の整備に向けて議論を進めている。
建設業にとっては、有形資産だけでなく技術力を含めた事業の継続・成長性が評価されることになる。経営者には将来性ある事業計画を金融機関に示し、具体化していく力が問われることになる。
これまでも、経営者保証の解除に当たっては、財務基盤の強化や経営の透明性の向上が求められてきた。新たな融資の選択肢が整備されたとしても、この点は変わらない。経営者保証の解除を目指す中小企業に対しては、専門家による支援制度も整備されている。価値ある企業を次代に引き継げるよう、経営者は適切に専門家や金融機関の力を借りて自社の経営を近代化することが必要だ。
残業規制まであと450日 「建設=長時間労働」は過去の遺物に 2023/1/6
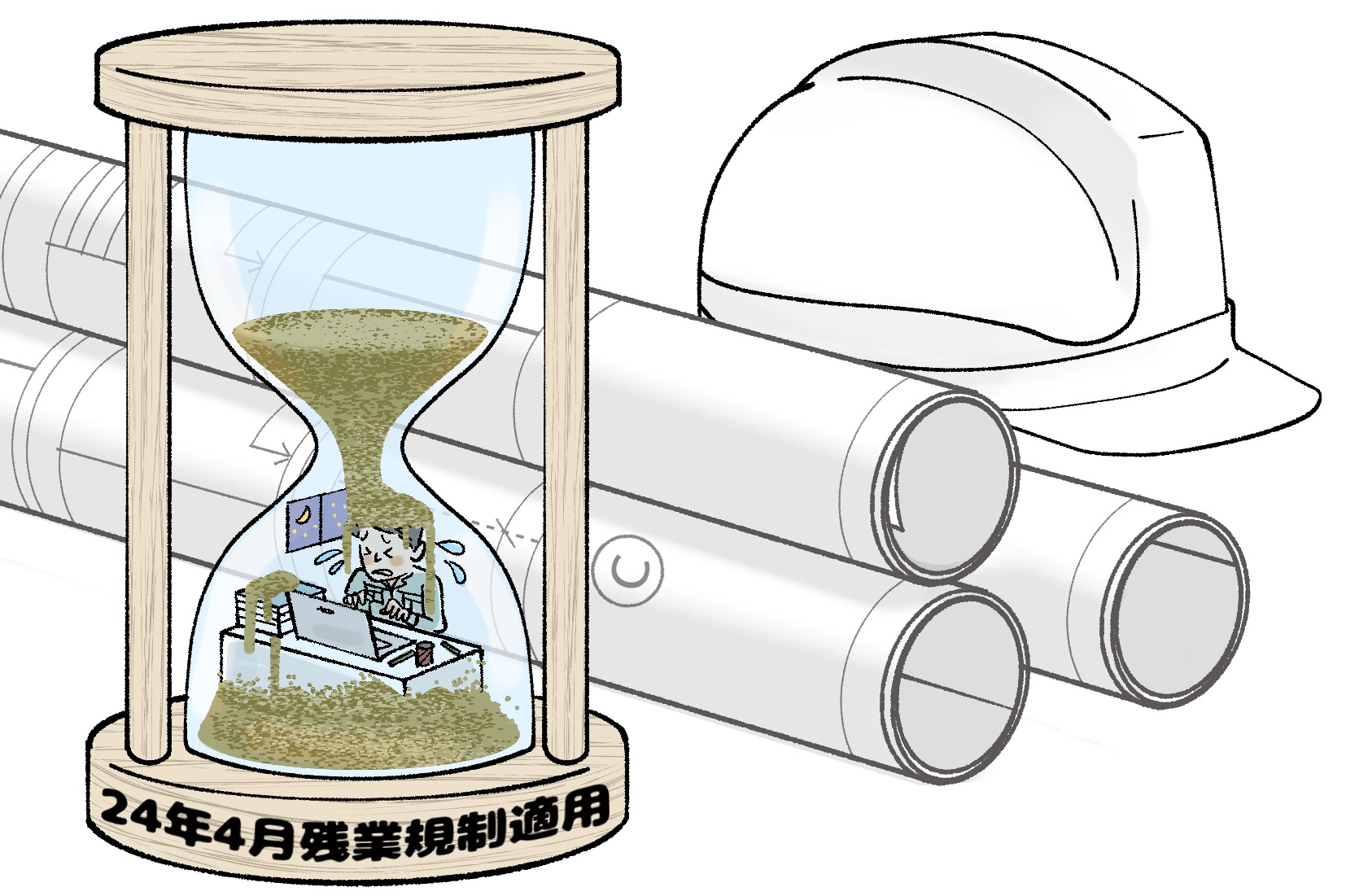
2023年の幕が開け、「時間外労働の上限規制」の建設業への適用まで1年3カ月を切った。建設現場の長時間労働是正に向け、現場で働く技能者・技術者の働き方改革が急がれる。
日本電設工業協会(電設協)の会員向けアンケートによると、規模の大きな企業ほど技術系職員の時間外労働が長くなりがちなことが分かった。従業員301人以上かつ資本金3億円超の大規模企業では、45%が「時間外労働45時間以上」となった。時間外労働の上限規制では、原則として超えてはならないとされる水準だ。
技術者の業務は現場業務4割、書類業務6割とされる。施工管理的な職務のウエートが大きくなり、書類などの作成に時間を取られるという。日中は現場に出るため、夕方以降に書類業務を行わざるを得ず、現場の長時間労働の大きな要因となっている。
技術者の働き方改革に向けて国土交通省は、建設業の新たな職域として民間企業が提案する「建設ディレクター」に関心を寄せる。バックオフィスで事務員がITを活用し、現場の技術者に代わって積算などの書類業務を手がけるものだ。バックオフィス業務ということで女性活躍にもつながっているという。
建設ディレクターの研修会に出席した国交省の見坂茂範技術調査課長は、「現場の生産性向上が急がれる中で、ICTの活用やバックオフィスとの分業体制は欠かせないものだ」とし、新たな職域の必要性や効果に期待をにじませた。
技術者の書類業務の負担が軽くなり、技術者がより現場業務に集中できるようになれば、現場の安全や品質の向上といった面でもよい効果が生まれる。若手技術者の育成に時間を割いたり、ICTをはじめとする新しい技術を勉強する時間もできる。個々がスキルアップすることで、より付加価値の高い現場環境の創出にもつながる。
人への投資という時代の潮流の中で、技術者の働き方改革は会社の存続に直結し、経営力を強める機会をももたらしてくれる。新たな職域の導入を考えてみるのも良さそうだ。
ただし、労働時間削減への取り組みに残された時間は、あまりない。いまだに長時間労働の是正に取り組めずにいる経営者がいるとしたら、一日も早く自社でできることを見極めることが必要だ。残業規制へのタイムリミットは迫っている。「建設=長時間労働」のイメージにつながる悪しき実態は、過去の遺物として23年度末までに封印しなければならない。
建設業向けに助成金 週休2日の導入後押し 2023/1/20
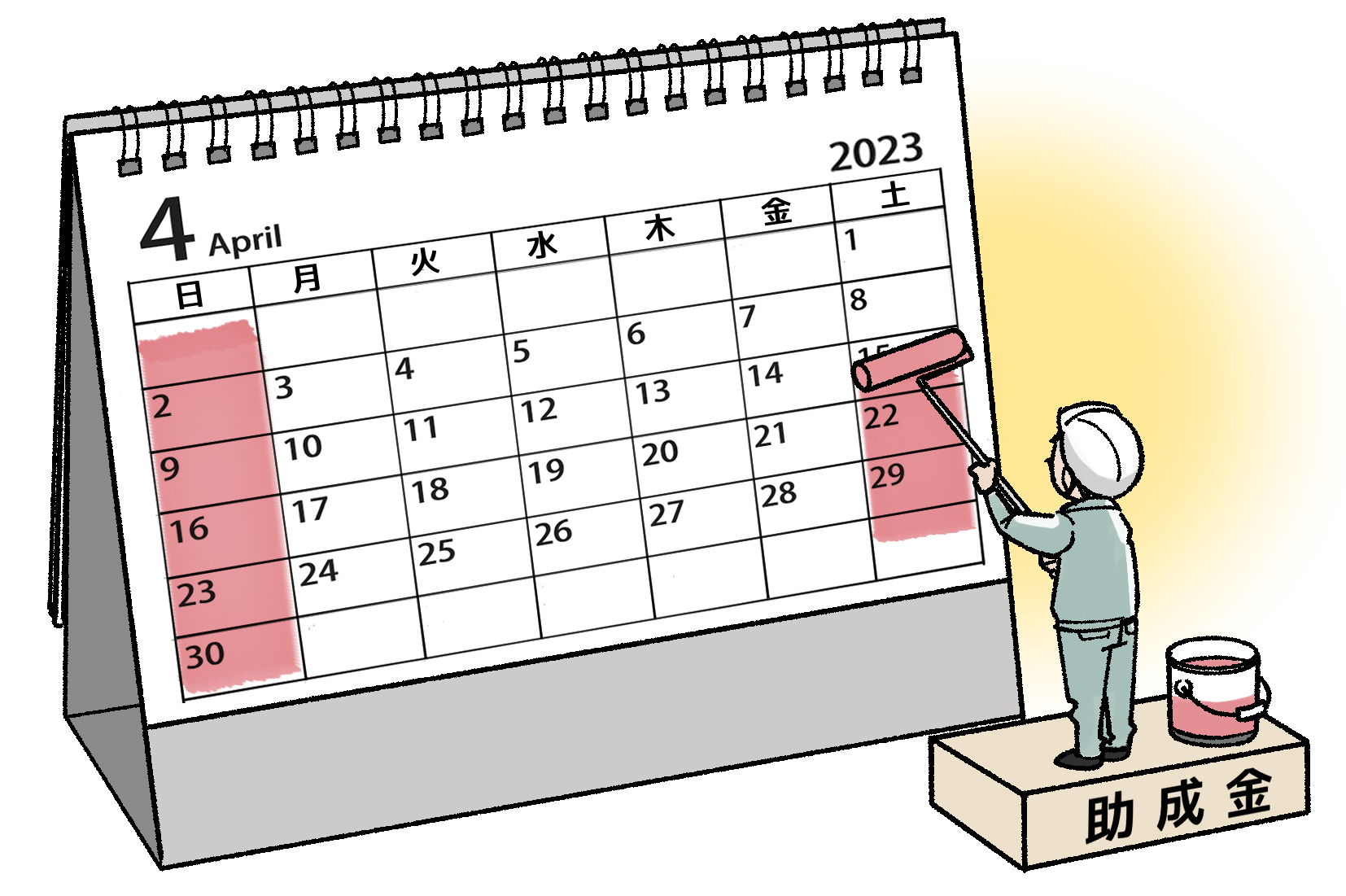
厚生労働省は、中小建設業の働き方改革を支援する新たな助成金を設ける。昨年末に決定した2023年度当初予算案に盛り込んだ。建設業でこれまで猶予されてきた時間外労働の罰則付き上限規制がいよいよ適用される24年4月を見据え、社内制度の整備や、労務管理に必要な機器の導入などを後押しする。ターゲットの一つには、週休2日制の導入拡大を掲げた。
厚生労働省はもともと、中小企業全般を対象として「働き方改革推進支援助成金」を通じた働き方改革支援を進めてきた。しかし、上限規制が猶予されてきた建設業などでいまだに「顕著な等時間労働の実態」があることから、「適用猶予業種等対応コース」を設け、業種の特性に応じたさらなる支援を講じることにした。予算案には43億円を計上している。
建設業の場合、資本金が3億円以下か、または常時使用する労働者が300人以下の企業が対象となる。また、36協定の締結など、一定の要件を設けている。
助成対象となる費用は幅広い。就業規則の作成・変更だけでなく、社会保険労務士をはじめとした外部専門家によるコンサルティングや、勤怠管理のための機器・ソフトウエアの導入、追加の人材確保に要する費用も含まれる。さらに、これまでの助成金でも、土木工事の積算システムや、測量機器・施工管理タブレットなど、事業の効率化につながるような機器の導入費用を助成した実績がある。
補助率は4分の3で、規模が30人以下であることなど一定の要件を満たせば5分の4に引き上げる。
ただし、助成額の上限は業種ごとに定めた成果目標の達成状況で決まる。建設業の場合は、現行の36協定で「月80時間超」の時間外・休日労働時間数を設定している場合、「60時間以下」に見直せば250万円、「60〜80時間」に見直せば150万円が上限となる。現行で「60〜80時間」を設定している場合、「60時間以下」に見直せば200万円が上限となる。
さらに、週休2日制工事を推進する観点から、上限額とは別枠の助成項目を設定。現行の社内体制が4週4休の場合、4週8休まで規定の休日を1日増やすごとに25万円を支給する。
時間外労働の罰則付き上限規制の適用まで、時間は限られている。厚労省は予算の成立後、可能な限り速やかに助成金の応募手続きを開始する考えだ。ホームページや業界団体を通じて助成金の活用をPRする他、申請のためのマニュアル整備も検討している。
時間外労働の上限規制に違反すると、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科される恐れがある。人材の定着・育成の観点からも違法な長時間労働は論外だ。工期設定など個社の努力では対応が困難な要因も影響するが、まずは助成金を活用しながら社内体制を整備することが重要となる。
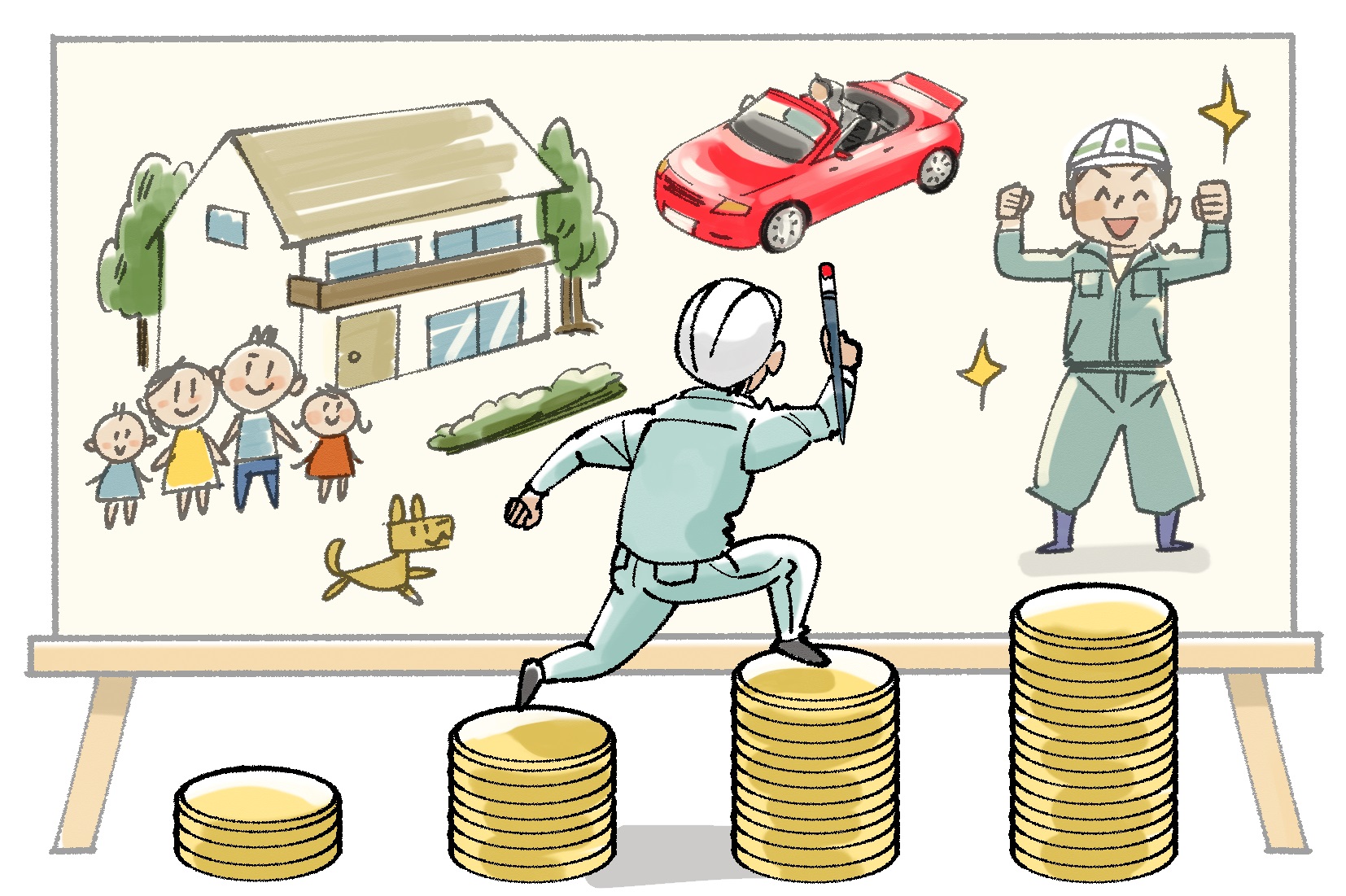 建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録技能者数が100万人を超え、技能者の3人に1人が利用する水準に至った。2019年の運用開始から3年半余りでの大台突破だ。斉藤鉄夫国土交通相は、「技能者のレベル別の賃金目安を示すことで、各職種の賃金の上昇を促していく」と今後を展望した。国交相が定例会見でCCUSに関して報告するのは異例だ。
建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録技能者数が100万人を超え、技能者の3人に1人が利用する水準に至った。2019年の運用開始から3年半余りでの大台突破だ。斉藤鉄夫国土交通相は、「技能者のレベル別の賃金目安を示すことで、各職種の賃金の上昇を促していく」と今後を展望した。国交相が定例会見でCCUSに関して報告するのは異例だ。 「後継者の候補はいるのに、事業の承継を拒否されている」。こんな悩みを抱える経営者は少なくない。その理由として、経営者個人が企業の連帯保証人となる「経営者保証」の影響が指摘されている。全国の建設業経営者の平均年齢は60歳に迫っており、事業承継が円滑に進まなければ、担い手不足に拍車をかけかねない。経営者保証によらない融資慣行の確立は喫緊の課題だ。
「後継者の候補はいるのに、事業の承継を拒否されている」。こんな悩みを抱える経営者は少なくない。その理由として、経営者個人が企業の連帯保証人となる「経営者保証」の影響が指摘されている。全国の建設業経営者の平均年齢は60歳に迫っており、事業承継が円滑に進まなければ、担い手不足に拍車をかけかねない。経営者保証によらない融資慣行の確立は喫緊の課題だ。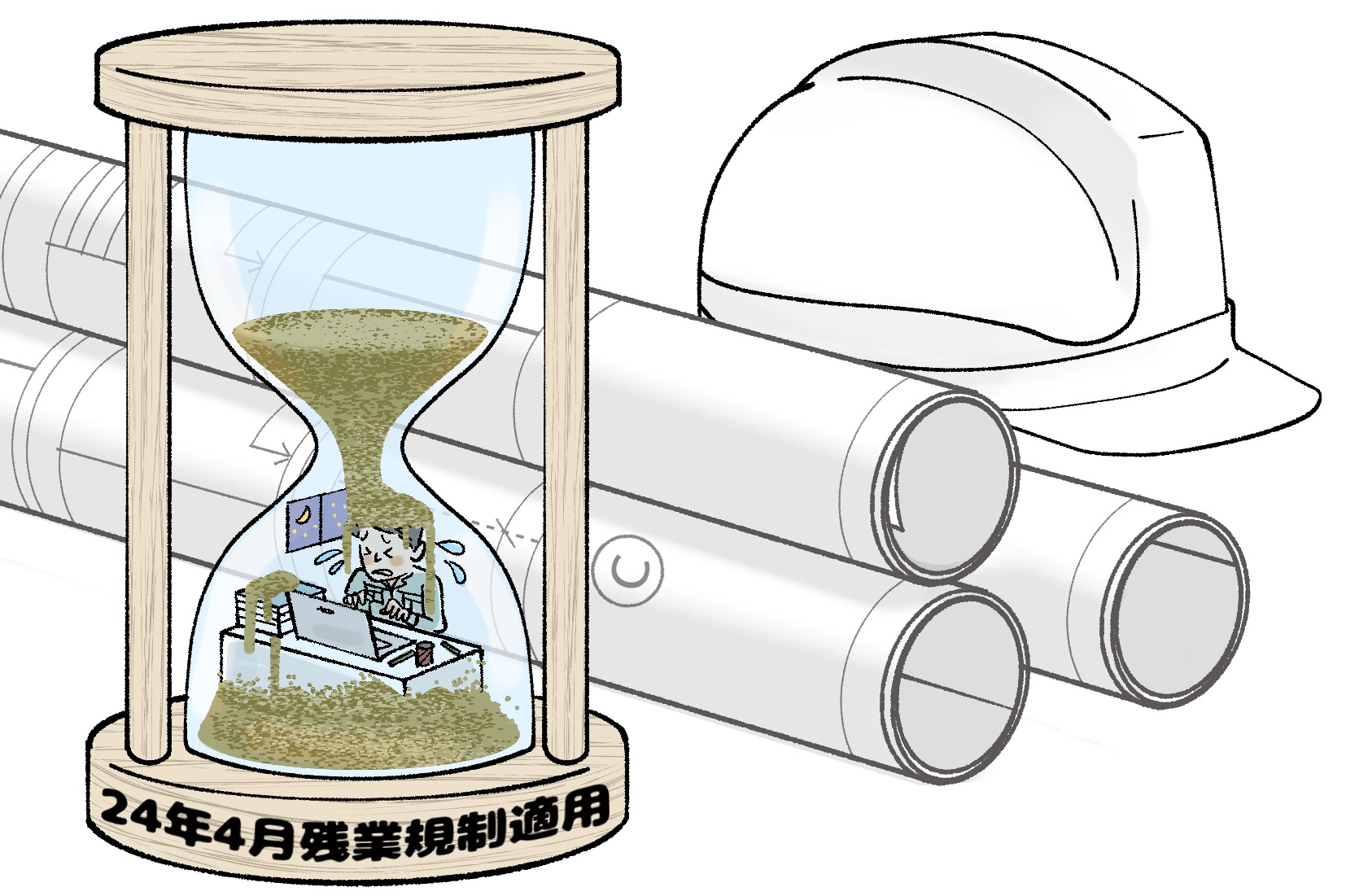 2023年の幕が開け、「時間外労働の上限規制」の建設業への適用まで1年3カ月を切った。建設現場の長時間労働是正に向け、現場で働く技能者・技術者の働き方改革が急がれる。
2023年の幕が開け、「時間外労働の上限規制」の建設業への適用まで1年3カ月を切った。建設現場の長時間労働是正に向け、現場で働く技能者・技術者の働き方改革が急がれる。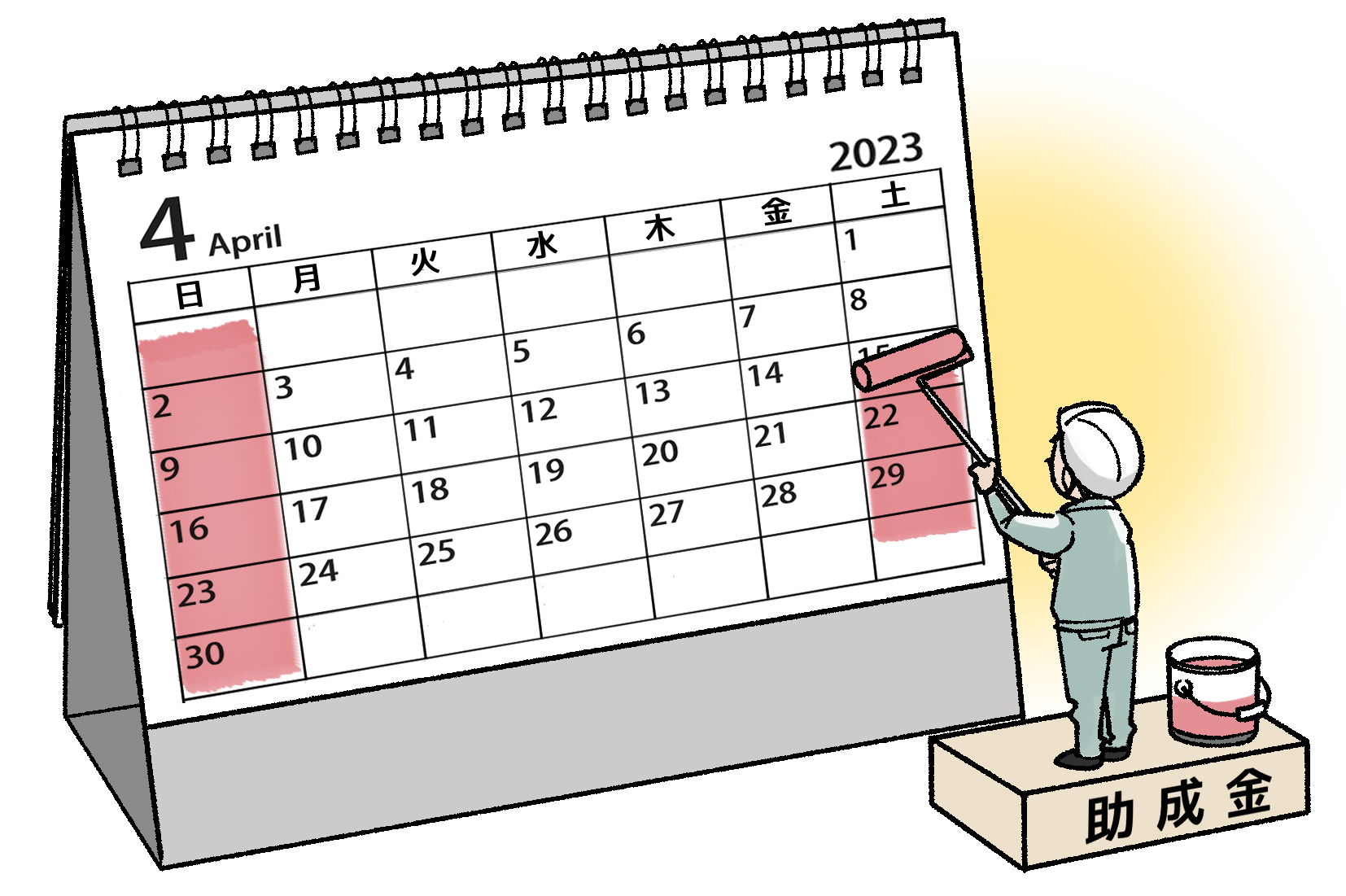 厚生労働省は、中小建設業の働き方改革を支援する新たな助成金を設ける。昨年末に決定した2023年度当初予算案に盛り込んだ。建設業でこれまで猶予されてきた時間外労働の罰則付き上限規制がいよいよ適用される24年4月を見据え、社内制度の整備や、労務管理に必要な機器の導入などを後押しする。ターゲットの一つには、週休2日制の導入拡大を掲げた。
厚生労働省は、中小建設業の働き方改革を支援する新たな助成金を設ける。昨年末に決定した2023年度当初予算案に盛り込んだ。建設業でこれまで猶予されてきた時間外労働の罰則付き上限規制がいよいよ適用される24年4月を見据え、社内制度の整備や、労務管理に必要な機器の導入などを後押しする。ターゲットの一つには、週休2日制の導入拡大を掲げた。 [New]建設資材価格マーケット(2025年4月)
[New]建設資材価格マーケット(2025年4月) 

 建設資材価格マーケット(2025年3月)
建設資材価格マーケット(2025年3月) 


 建設資材価格マーケット(2025年2月)
建設資材価格マーケット(2025年2月) 




 建設資材価格マーケット(2025年1月)
建設資材価格マーケット(2025年1月) 



 建設資材価格マーケット(2024年12月)
建設資材価格マーケット(2024年12月) 

 建設資材価格マーケット(2024年11月)
建設資材価格マーケット(2024年11月)